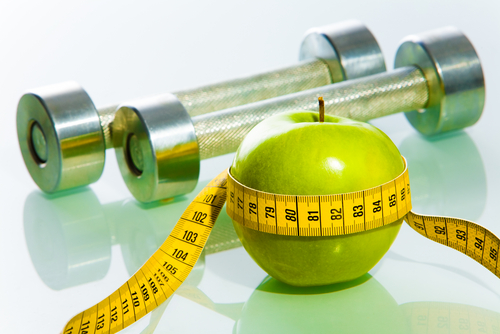塩分をカラダの外に排出してくれる【カリウム】
カリウムは、野菜などに多く含まれている栄養素で、ナトリウム(食塩)をカラダの外に排出する働きがあるため、正常な血圧を保つために必要な栄養素です。

カリウムの働き
カリウムの主な働きは以下の通りです。
①体内の水分のバランスを調整する
細胞内の水分にはカリウムが、細胞外の水分にはナトリウムが多く含まれ、それぞれがポンプのように働き、常に適正な濃度を保つよう水分バランスを調整しています。また、細胞の浸透圧を調整して一定に保つ働きもあります。
②ナトリウムによる血圧上昇を抑制する
ナトリウムとカリウムは細胞内液と外液の浸透圧を均等に保つ役割があります。ナトリウムが過剰になると、浸透圧が上がり血圧が上昇しますが、このときにカリウムが十分にあると、余分なナトリウムの尿中への排泄をしやすくし、食塩の摂りすぎを調整するのに役立ちます。そのため、高血圧の予防に役立ちます。
③筋肉の働きを正常に保つ
カリウムは神経の興奮性や筋肉の収縮に関わっています。ナトリウムと相互に作用して、筋肉の動きを正常に保つ働きがあります。
カリウムの摂取目標量
カリウムの摂取目標量は、以下の通りです。妊娠期・授乳期でも目標量に変化はありません。
| 年齢・性別 | 摂取目標量(1日) |
| 15歳以上・男性 | 3000mg |
| 15歳以上・女性 | 2600mg |
| 妊娠期 | 2600mg |
| 授乳期 | 2600mg |
血圧が気になる方の場合
血圧のリスクを減らすためのカリウム摂取推奨量は、3510mgとされています。血圧が気になる方は意識的に摂るようにしましょう。
※腎機能障害・糖尿病性腎症の場合は、カリウムの排泄に支障をきたすことがあるため、カリウムの摂取量に制限がかかる場合があります。摂取量は主治医の診断を仰ぐようにしてください。
欠乏・過剰について
カリウムはさまざまな食材に含まれているので、普通の食事で欠乏することはあまりありません。
また過剰摂取についても、腎臓の機能が正常であり、特にカリウムのサプリメントなどを使用していなければ、心配する必要はほとんどありません。
カリウムが多く含まれる食材・食事
カリウムはさまざまな食材に広く含まれていますが、特に葉野菜や芋類に多く含まれています。
| ほうれん草(100g・1/3束) | 690mg |
| 長芋(100g・約5cm)・アボカド(100g・約1/2個分) | 590mg |
| めかじき・さわら・アジ(焼き魚) | 540~630mg |
| モロヘイヤ(100g・1束) | 530mg |
| あゆ・真鯛(焼き魚) | 430~500mg |
| 焼き芋(100g・約1/2本)・小松菜(100g・1/3束) | 500mg |
| ブロッコリー(100g・約1/3株) | 460mg |
| 里芋(70g・中くらいのサイズ1個分) | 450mg |
| 豚ひれ肉 | 400~430mg |
| 納豆(1パック50g) | 345mg |
※特に記載のないものは、食品100gあたりの含有量を表示しています。
⇒栄養士が伝授!野菜350gのとり方
カリウムが含まれる飲み物
カリウムは野菜に多いため、野菜を使った飲み物などにも含まれていて、手軽に効率よく摂取できます。果汁・野菜ジュースを飲む場合は、栄養成分表示を確認し、食塩や砂糖が含まれていないものを選ぶのがおすすめです。
| 野菜100%ジュース(200ml・紙パック1本) ※ミックスジュース・トマトジュース(食塩不使用) |
400~520mg |
| 牛乳(200ml・コップ1杯) | 300mg |
摂取のポイント
カリウムとナトリウムのバランスが崩れると、ナトリウムがうまく排出できなくなります。その結果、血圧が上がり、さまざまな病気のリスクも上がってしまいます。病気を予防するためにもカリウムを含む野菜や果物などの食品をとり、お酢やゆず・レモンの絞り汁、胡椒、からし、わさび、カレー粉などを上手に使って普段の食事から減塩を心がけましょう。
外食中心の食生活や濃い味付けを好む方は、サイドメニューにサラダを、味噌汁に葉物野菜や芋類を、おやつに焼き芋などを積極的にとり入れ、カリウムとナトリウムの摂取バランスに気を付けてみるとよいですね。
【参考・参照】
厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2025年版)〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html?s=31〉(最終閲覧日:2025/3/28)
文部科学省 日本食品標準成分表2020年版(八訂)〈https://fooddb.mext.go.jp〉(最終閲覧日2025/3/28)
※本記事は、2014年8月15日に公開された記事を再編集しました。(2025年5月1日)